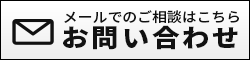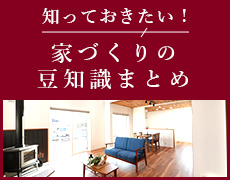自分の年収で住宅ローンはいくら借りられる? 無理の無い返済を行うためのポイント
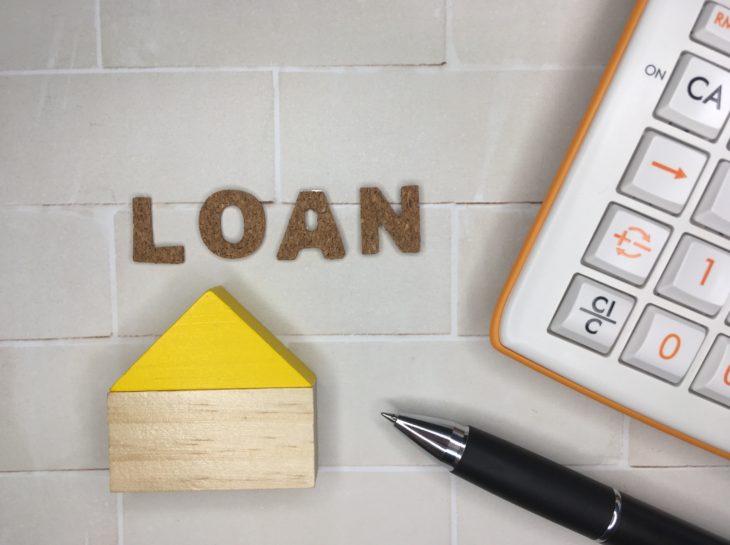
自分の年収で住宅ローンはいくら借りられる? 無理の無い返済を行うためのポイント
住宅ローンを活用すれば、自己資金の少ない方でも理想のマイホームを購入できるチャンスが広がります。
しかし、住宅ローンには「借入可能額」があるため、いくらでも融資が受けられるわけではありません。
「自分はいくらまで借り入れできるのか?」と考えている方へ。
今回は、住宅ローンの借入可能額を決める要素や年収別の借入可能額の目安をお伝えするとともに、無理のない返済プランを立てるうえで知っておきたいポイントを紹介します。
目次
-
1.住宅ローンはいくらまで借りられるのか?3つのポイント
金融機関の審査では、住宅ローン申込者の借入可能額を「収入」「返済負担率」「借入期間(返済期間)」という大きく3つの要素を使って試算しています。
収入
収入とは、現在の年収のことです。年収が高ければ審査に通るというわけではなく、「長期間にわたって安定した収入が得られる」ことがポイントになります。
そのため、勤務先や勤続年数も、審査で重視される項目です。
返済負担率
返済負担率とは、年収に占める住宅ローン返済額の割合のことです。
金融機関にもよりますが、返済負担率は30%前後に設定しているところが多くみられます。
ただ、無理のない返済プランを立てるには25%で設定するとよいでしょう。
仮に年収が400万円で返済負担率を25%とした場合、年間の住宅ローン返済額は100万円、毎月の支払額は8万円ちょっとです。
家庭の状況にもよるので、生活費や教育費なども考えた上で、ゆとりをもって決めることが大切です。
借入期間(返済期間)
住宅ローンは、最長で35年まで借り入れできる商品が多いです。
ただし、借入期間は申込者の年齢にもよります。
先述の通り、長期間にわたって安定した収入があることが金融機関の審査基準の一つです。
これは、「定年までに完済を求める」という意味でもあります。
40歳の方で定年が65歳であれば、借入期間は25年です。
期間が短くなれば毎月の返済額がアップしますから、借入額の調整や頭金を増やすといった工夫が必要になってくるでしょう。
金利負担のことも考えよう
借入期間が長くなれば、金融機関に支払う金利負担(利息)も多くなります。
2022年現在、住宅ローンの金利はとても低く、固定金利だと1%台、変動金利なら1%以下の商品もたくさんあります。
しかし、いくら低金利でも35年も借り入れると利息分だけで数百万円にもなることは覚えておきたいポイントです。
仮に3,000万円を固定金利1%で35年借り入れたときの利息は約557万円にもなり、これも毎月の返済額に加わります。
注意したいのが、変動金利の住宅ローンを利用する場合。
市場金利がアップすれば、住宅ローンの金利も上がりますから返済負担が重くなります。
金利が上がっても返済が滞ることがないよう、借入額を決める際には余裕を持った額にすることも大切です。 -
2.年収ごとの住宅ローン借入可能額の目安表
「年収」「返済負担率」「借入期間」の3つの要素があれば、おおよその借入可能額が確認できます。
ここでは、住宅ローンの借入可能額を年収別に試算しました。
なお、試算にあたり返済負担率は25%、返済期間は35年、金利は全期間固定で1.4%とします。
シミュレーション参考:住宅保証機構「住宅ローンシミュレーション」https://loan.mamoris.jp/index.html
年収300万円の借入可能額は2,074万円
年収300万円の借入可能額の目安は、2,074万円です。
すでに土地を所有されている方なら、理想に近い注文住宅が建てられる金額でしょう。
なお、2,074万円を35年間で借り入れると金利負担分だけで約550万円になり、毎月の返済額は62,491円になります。
ボーナスを含めて年収300万円の方だと、月々の給与は手取りで18万円くらいでしょうから、住宅ローンを差し引いた額は12万円弱しか残りません。
一般的に、年収が少ないほど返済負担率は下げた方が良いといわれます。
無理のない返済プランを考えるなら、返済負担率を20%で設定しても良いでしょう。
借入可能額は約1,659万円になりますが、毎月の返済額は4万9,987円にまで抑えられます。
年収400万円の借入可能額は2,765万円
年収400万円の借入可能額の目安は、2,765万円です。
土地探しから始める場合でも、注文住宅が手に届くのではないでしょうか。
金利負担を含めたトータル返済額は約3,500万円、毎月の返済額は8万3,312円です。
年収400万円の場合、毎月の給与は25万円弱くらいでしょうから、ローンを差し引いても15万円以上は手元に残ります。
この額だと厳しいという方なら、返済負担率を20%に下げて考えると良いでしょう。
年収500万円の借入可能額は3,457万円
年収500万円だと借入可能額は3,457万円になり、住まいの選択肢は増えることでしょう。
趣味の空間など、理想に近い注文住宅を建てられる可能性もあります。
トータル返済額は約4,375万円、毎月の返済額は104,162円です。
年収500万円だと毎月の給与は30万円弱くらいでしょうから、ローン支払後の生活にも余裕が出てきます。
だからといって、返済負担率を上げない方が無難です。
仮に30%だと借入可能額は4,148万円になるものの、毎月の返済額は12万円を超えます。
将来への貯蓄にも充てられるよう、無理のない計画を立てることが大切です。
年収600万円の借入可能額は4,148万円
年収600万円だと、借入可能額は4,148万円です。
ワンランク上の注文住宅を検討できる額ではないでしょうか。
トータル返済額は約5,249万円、毎月の返済額は124,983円になりますが、毎月の給与は30万円を超えるでしょうから、ローン支払後の生活資金にも余裕があるでしょう。
ただ、返済負担率を30%に上げると毎月の返済額は約15万円になります。
ローンを差し引いた残額が20万以下になっても、余裕がある家庭なら30%で検討しても良いでしょうが、ちょっと苦しいと思ったら無理をせず貯蓄に回し、繰り上げ返済に充てるのも一手です。
年収700万円の借入可能額は4,839万円
年収700万円の方の借入可能額は、4,839万円。
毎月の返済額は14万5,803円です。
ローン返済以外に毎月20万円以上は使えますから、余裕があれば返済負担率を30%にアップしても良いかもしれません。
30%だと借入可能額は5,800万円を超え、より理想の家を手に入れやすくなるでしょう。
ただ、返済負担率が30%を超えると給与の半分くらいが住宅ローン返済に充てることになりますから、無理なプランは禁物です。 -
3.限度額まで借り入れるメリット
借入可能額の限度額いっぱいまで融資が受けられたら、マイホームの選択肢が広がり、より理想に近い家を手に入れられます。
予算があれば、それだけ優れた建材や性能の高い設備を導入できますから、住み始めてからの満足度も高まるでしょう。
また、土地探しから始める方であれば立地の良い物件を購入できる可能性が高まります。
駅前や商業施設などの近くであれば地価も下がりにくく、資産価値を保ちやすいので、将来売却する際にも有利です。 -
4.限度額まで借り入れるデメリット
限度額いっぱいまで借り入れると、不安になるのが毎月の返済額です。
ローンの返済期間は30年以上も続きます。
長い人生の間に、いつ何が起きるかわかりません。
病気や事故などで収入が減ることがあるかもしれませんし、子どもの教育費や親の介護など想定以上に出費が増え続けることだってあるでしょう。
収入が減ったり支出が増えたりしても、住宅ローンの返済は変わらず続きます。
万一に備えて貯蓄もできるよう、余裕を見て借り入れることが無理のない返済を続ける鉄則なのです。 -
5.借りられる金額と返せる金額は違う
「現在の収入で、住宅ローンはいくら借りられるか?」をシミュレーションして知るのは大切なことですが、それよりも重要なのは「いくらまでなら返せるのか」という視点を持つことです。
たとえば年収400万円の方の場合、上記のシミュレーションでは借入可能額は2,765万円でも、利息を含めると約3,500万円も金融機関に支払うことになります。
このシミュレーションは固定金利ですが、もし変動金利で契約し、将来の金利がアップした場合、返済額は4,000万円を超えることも考えられます。
そうなれば、毎月の返済額は10万円前後になるかもしれません。
金利のアップとともに収入も増えるなら心配はありませんが、収入に変化がなければローン返済が家計を圧迫します。
場合によっては返済が滞る事態に陥り、最悪の場合はマイホームを手放し競売にかけられることもあり得る話です。
このような事態にならないよう、毎月返済が続けられる額を検討し、それにあわせて借入額を決めることも無理のない返済プランを立てるポイントでしょう。
限度額よりもやや少なく、余裕を持つことが大切です。
住宅ローンの返済方法には、毎月の返済とは別にまとまった資金を元金の返済に充てる「繰り上げ返済」もあります。
繰り上げ返済を使えばトータルの返済額を減らせますから、返済期間を短くしたり毎月の返済額を減らしたりすることも可能です。
こうした手段も上手に使いながら、住宅ローンと付き合っていきましょう。 -
6.まとめ
住宅ローンを扱う金融機関のホームページには、借入可能額を試算できるシミュレーションページがあります。
ここに年収や返済負担率、返済期間などを入力すれば、いくら借り入れできるかが簡単にわかりますから、気になる方は利用してみましょう。
ただ、その際に注意したいのが「返済負担率を上げ過ぎないこと」。
借入額を増やそうと、無理に30%や35%に引き上げたい気持ちもわかりますが、「借りたお金は返さなければいけない」という視点を忘れてはいけません。
返済負担率は25%くらいに設定すると、無理のない返済プランを立てやすくなりますから、欲を出さずシミュレーションされることをおすすめします。