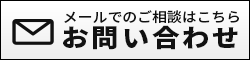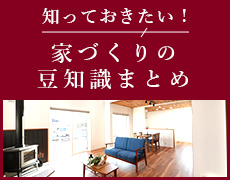年収500~600万円で3,500~4,000万円の住宅ローンを組むときの返済は?
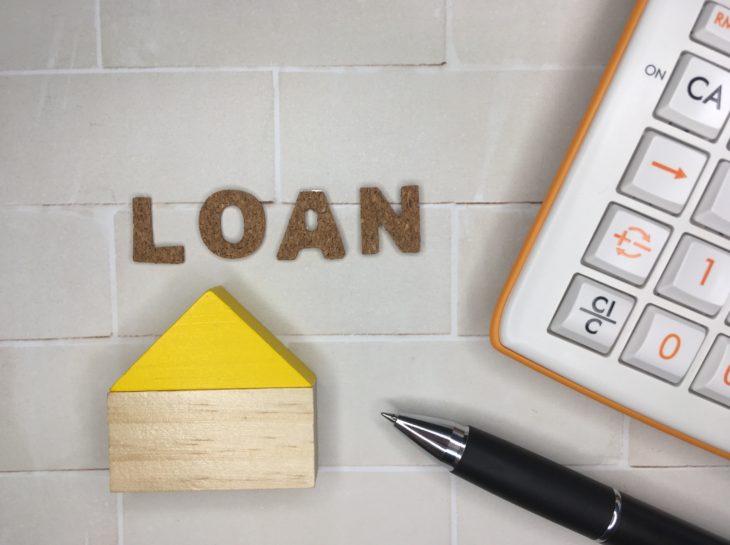
年収500~600万円で3,500~4,000万円の住宅ローンを組むときの返済は?
住宅ローンの利用を検討するとき、「今の年収でどれくらい借り入れできるか?」と不安に思われている方は少なくないでしょう。
共働き世帯であれば、世帯年収は500~600万円くらいの方が多いと思います。
この所得の方々が借り入れできる目安の返済可能額は、どれくらいなのでしょうか。
一例として、年収500~600万円の方が3,500~4,000万円の住宅ローンを借り入れられるかを検証してみます。
目次
-
1.年収500~600万円の返済可能額の目安は?
まずは、年収500~600万円で借り入れできる住宅ローンの返済可能額を試算します。
試算するにあたり、前提条件は次の通りです。
・返済方法:元利均等
・返済期間:35年
・金利:1.4%(全期間固定)
・返済負担率:25%
この条件で、年収500万円と600万円の返済可能額および毎月の返済額は、以下の通りです。
●年収500万円の返済可能額(目安)
・住宅ローン返済可能額:3,457万円
・毎月の返済額:10万4,162円
●年収600万円の返済可能額(目安)
・住宅ローン返済可能額:4,148万円
・毎月の返済額:12万4,983円
参考:住宅保証機構「住宅ローンシミュレーション」
https://loan.mamoris.jp/index.html
手取り額から返済可能額を考えると?
年収500~600万円といっても、税金や保険料などを差し引くと手取り額は400~480万円くらいになるでしょう。
返済可能額を検討する際には手取り額から試算した方が、ゆとりある返済プランを立てやすくなります。
では、先ほどと同じ条件で手取り額400万円と480万円の返済可能額を求めてみましょう。
●手取り400万円(年収500万円)の返済可能額の目安
・住宅ローン返済可能額:2,765万円
・毎月の返済額:8万3,312円
●手取り480万円の(年収600万円)返済可能額の目安
・住宅ローン返済可能額:3,318万円
・毎月の返済額:9万9,974円
参考:住宅保証機構「住宅ローンシミュレーション」
https://loan.mamoris.jp/index.html
手取り額で求めると、返済可能額は約700~800万円も減ってしまいます。
ただ、毎月の返済額は2万円前後も抑えられますから、返済が始まってからの家計は余裕が生まれるでしょう。 -
2.3,500~4,000万円の住宅ローンの返済額はいくら?
続いて、3,500~4,000万円の住宅ローンを借り入れたときの返済額を考えます。
前提条件は上記と同じく、元利均等方式、返済期間は35年、金利は全期間固定の1.4%とします。
この条件で、3,500万円または4,000万円の住宅ローンを利用するとき、トータル返済額と毎月の返済額は以下の通りです。
●借入額3,500万円の返済額
・トータルの返済額:4,429万2,292円
・毎月の返済額:10万5,458円
●借入額4,000万円の返済額
・トータルの返済額:5,061万9,853円
・毎月の返済額:12万523円
参考:住宅保証機構「住宅ローンシミュレーション」
https://loan.mamoris.jp/index.html -
3.手取り400~480万円で3,500~4,000万円の返済は可能か?
住宅ローンの返済可能額を、税金や保険料を含めた年収で試算すると、500万円の方なら3,457万円、600万円なら4,148万円ですから、審査に通る可能性が高いと考えられます。
ただし、3,500~4,000万円を借り入れたときの毎月の返済額から見た場合、現実的に難しいと感じるかもしれません。
上記の試算より、3,500万円の住宅ローンを借り入れた場合の毎月の返済額は10万5,458円です。
一方、手取り400万円(年収500万円)を単純に12ヵ月で割ると約33万円ですが、ボーナスを含めた年収の場合は毎月の給与が25~28万円くらいの方も多いでしょう。
この給与の4割近くをローン返済に充てると、残り額で生活費をやりくりするのが厳しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
手取り480万円(年収600万円)であれば、毎月の給与は30万円を超えるでしょうから3,500万円の住宅ローンでもゆとりある返済プランを立てられるでしょう。
ただ、4,000万円を借り入れると毎月の返済額が約12万円ですから、家計の状況によっては厳しくなる方も出てくるのではないでしょうか。
もちろん、家計の状況は人それぞれですから、現在の生活費や貯蓄から住居費の予算を逆算して求めることも大切です。 -
4.元金均等返済なら返済額を抑えられる?
住宅ローンの返済方法には、「元利均等」と「元金均等」があります。
元利均等とは、利息を含めたトータルの返済額を毎月均等に返済していく方法。
一方の元金均等は、元金を均等に分けた額に借入残高に応じた利息を足した額を返済していく方法です。
毎月の返済額は、同じ額を返済していく元利均等に対して、元金均等は借入残高の多い返済初期は高くなり、完済が近づくにつれ安くなっていくことが特徴です。
どちらも返済額は変わらないと思われがちですが、実は元金均等の方がトータルの返済額を抑えられる傾向があります。
これまでの試算では、トータルの返済額の多くなる元利均等で求めた額ですが、これを元金均等で求めるとどうなるのでしょうか。
同じ条件(返済期間35年、全期間固定金利1.4%)で、3,500~4,000万円の住宅ローンを元金均等で返済する場合をシミュレーションします。
●借入額3,500万円の返済額(元金均等)
・トータルの返済額:4,359万5,245円
・毎月の返済額:12万4,166~8万3,570円
●借入額4,000万円の返済額(元金均等)
・トータルの返済額:4,982万3,147円
・毎月の返済額:14万1,904~9万5,389円
参考:keisan「ローン返済(毎月払い)」
https://keisan.casio.jp/exec/system/1256183644トータル返済額は、元金均等の方が70~80万円も抑えられます。
ただし、返済が始まる当初の毎月の返済額を見ると12~14万円になるため、元利均等よりも2万円前後高くなるのが注意点です。
元金均等の住宅ローン審査は、当初の返済額で判断されますから、年収などの要件が満たず金融機関の審査に通らない可能性もあります。
審査に通りやすくするなら、元利均等を選ぶのもポイントです。 -
5.住宅ローン控除は家計の足しになる?
住宅ローンを利用してマイホームを購入された方には、「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」という節税制度が受けられます。
住宅ローン控除とは、年末のローン残高に一定の控除率をかけた額が、所得税や住民税から還付される制度です。
一例として、年収600万円で扶養家族がいる家庭で4,000万円の住宅ローンを借り入れた場合、住宅ローン控除の還付金は初年度で25万円前後が見込めます。
なお、控除期間は最長13年間です。
この還付金を家計の足しにしようと、期待されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なかには、控除額で住宅ローンの返済に充てようと考えている方がいるかもしれません。
しかし、控除額は納めた税金から還付されるものですから、納税額以上の還付金は受け取れません。
それに、控除額はローン残高に応じて決まりますから年々減っていきます。
住宅ローン控除は家計の足しになりますが、住宅ローンの返済に充てるには無理があるので、ローンの返済計画に含まない方が無難でしょう。 -
6.住宅ローン返済で家計を圧迫させないためには?
住宅ローンは、現在の収入や貯蓄だけではマイホームを購入できない人をサポートする、便利な商品です。
しかし、収入に見合わない額を借り入れると、返済が始まってから家計を圧迫させ、苦しい生活を余儀なくされるケースも散見されます。
生活が苦しくなる理由は人それぞれですが、たとえば、ボーナスが減るなどの収入の減少や家族が増えて支出が増加するといったことが多いようです。
住宅ローンの返済は30年前後と長期にわたります。
その間に、家計に大きな影響を与えるような予測できない事態に遭遇する可能性は誰にでもあるでしょう。
そのような変化があっても、毎月一定額の住宅ローンの返済は変わらず続きます。
住宅ローンの返済で家計を圧迫させないためには、長期的な視野をもって「ゆとりをもって返済計画を立てる」こと。
病気やケガなど不測の事態は予測できませんが、産休・育休で収入が減る時期とか、子どもの進学で教育費が増える時期といったライフイベントは予測できることです。
こうした時期に、「いくらまでなら住宅ローンの返済に充てられるか」という見通しを立てることで、”住宅ローン地獄”のリスクを避けられます。
家計の変化に対応できる返済額を把握した上で、返済可能額を検討することも重要なポイントといえるのです。 -
7.まとめ
年収500~600万円で、3,500~4,000万円の住宅ローンを借り入れることは可能です。
ただ、住宅ローンの審査では年齢や勤続年数、キャッシングなどほかのローン借入状況といった基準をクリアすることも条件になりますから、年収の要件を満たしても審査に通らない可能性があることは把握しておきましょう。
また、家計の状況は人それぞれ異なりますから、現状や将来の家計を見越した上でゆとりある返済計画を立てることが重要になります。
「少しでも借入額を増やして理想の家を手に入れたい」という気持ちもわかりますが、住宅ローンの返済が滞ると最悪の場合、家を差し押さえられて売却せざる得ない状況になることもあります。
どんなことがあっても返済できる額こそが適切な借入額ですから、しっかり計画を立てたうえで身丈に合った借入額を決めましょう。